 松本会長
松本会長
 松本会長
松本会長
令和7年度全国医師会産業医部会連絡協議会(主催:日本医師会、日本産業衛生学会、後援:厚生労働省、労働者健康安全機構、産業医科大学、産業医学振興財団、中央労働災害防止協会)が7月3日、「メンタルヘルス対応能力向上のための産業医支援」をテーマとして、日本医師会館大講堂にてWEB会議とのハイブリッド形式で開催された。
協議会は松岡かおり常任理事の司会で開会し、松本吉郎会長と武林亨日本産業衛生学会理事長がそれぞれあいさつした。
松本会長は、先の通常国会において労働安全衛生法が改正され、労働者数が50人未満の事業場においてもストレスチェックが義務化されることになったことに言及。その対応のため、今回の協議会の趣旨を、(1)メンタルヘルス対応に苦手意識がある産業医もいる、(2)ストレスチェックを実施する事業場の数が大幅に増加する―ことを踏まえ、地域医師会や産業保健関係団体が実施してきた支援策を紹介することにしたと説明し、協議会の成果が今後の産業医活動の一助となることに期待を寄せた。
中央情勢報告
 その後はまず、佐々木孝治厚労省労働基準局安全衛生部労働衛生課長より中央情勢報告が行われた。
その後はまず、佐々木孝治厚労省労働基準局安全衛生部労働衛生課長より中央情勢報告が行われた。
同課長は、(1)労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部の改正、(2)メンタルヘルス対策、(3)治療と仕事の両立支援、(4)一般健康診断、(5)熱中症対策、(6)その他―について概説。
また、国による産業保健活動総合支援事業として、「産業保健総合支援センター(産保センター)」「地域産業保健センター(地産保)」の活動内容を紹介。今後、ストレスチェックの対象事業場が拡大される中でストレスチェックの実施が負担とならないよう、実施体制等に関するマニュアルの作成や地産保の体制の強化等の対応を行った上で、法律の公布日(令和7年5月14日)から3年以内に施行する予定である旨を説明した。
シンポジウム
 続くシンポジウムでは、相澤好治日本医師会産業保健委員会委員長/北里大学名誉教授が座長を務め、3名のシンポジストが講演を行った。
続くシンポジウムでは、相澤好治日本医師会産業保健委員会委員長/北里大学名誉教授が座長を務め、3名のシンポジストが講演を行った。
 江口尚産業医科大学教授は、従業員数50人未満の事業場におけるメンタルヘルス対策の進め方等について概説。精神障害を原因とする労災の申請件数が依然として増加傾向であることなどが、従業者数50人未満の事業場におけるストレスチェック義務化の背景であると説明。その上で、小規模事業場においてメンタルヘルス対策を推進するにしても、スタッフの確保が困難であることが多いため、地産保等の外部資源の積極的な活用が有効であるとした。また、メンタルヘルスケアの具体的な進め方として、「まずは事業者が『メンタルヘルス不調』について理解するとともに、厚労省による指針を参照しながら、対策の具体的な進め方を把握することが重要である」と述べた。
江口尚産業医科大学教授は、従業員数50人未満の事業場におけるメンタルヘルス対策の進め方等について概説。精神障害を原因とする労災の申請件数が依然として増加傾向であることなどが、従業者数50人未満の事業場におけるストレスチェック義務化の背景であると説明。その上で、小規模事業場においてメンタルヘルス対策を推進するにしても、スタッフの確保が困難であることが多いため、地産保等の外部資源の積極的な活用が有効であるとした。また、メンタルヘルスケアの具体的な進め方として、「まずは事業者が『メンタルヘルス不調』について理解するとともに、厚労省による指針を参照しながら、対策の具体的な進め方を把握することが重要である」と述べた。
 渡辺洋一郎日本精神科産業医協会代表理事は、ストレスチェック制度の趣旨について、「労働者のストレス症状」ではなく「職場環境」をチェックするものであると説明。従業員のストレス状況を改善し、働きやすい職場を実現することが産業医の使命であることを強調した。
渡辺洋一郎日本精神科産業医協会代表理事は、ストレスチェック制度の趣旨について、「労働者のストレス症状」ではなく「職場環境」をチェックするものであると説明。従業員のストレス状況を改善し、働きやすい職場を実現することが産業医の使命であることを強調した。
また、働き方改革が労働者のメンタルヘルスにもたらす負の影響(仕事量が減少しない中での労働時間の短縮は精神的負担感を増大させる等)について解説した上で、働き方や価値観の変化に応じて生じる新たな課題に、企業、労働者、産業医がそれぞれ対応していく必要があるとの認識を示した。
 山内直人千葉産業保健総合支援センター相談員は、近年、産業医の業務として労働者のメンタルヘルスに関係する面談・面接の機会が増加傾向にあり、面談・面接に当たってはその目的を意識することが重要になると説明。メンタルヘルスケアが専門ではない産業医が労働者の問題に対応する場合には、労働者との縦の関係として解決策を提示するのではなく、横の関係として問題解決のパートナーであることを意識することや、人格と問題を切り分けた上で、解決を目指す必要性があることを強調した。
山内直人千葉産業保健総合支援センター相談員は、近年、産業医の業務として労働者のメンタルヘルスに関係する面談・面接の機会が増加傾向にあり、面談・面接に当たってはその目的を意識することが重要になると説明。メンタルヘルスケアが専門ではない産業医が労働者の問題に対応する場合には、労働者との縦の関係として解決策を提示するのではなく、横の関係として問題解決のパートナーであることを意識することや、人格と問題を切り分けた上で、解決を目指す必要性があることを強調した。
最近の活動報告
 シンポジウムに続き、「最近の活動報告」として、森永幸二佐賀県医師会副会長が佐賀県における産業医部会の取り組みを紹介。まず、県内事業場を規模別に見ると、従業者数50人未満の事業者が約97%を占めており、中小企業を中心に産業保健活動を考える必要があるとした。また、2019年の働き方改革関連法施行を受け、佐賀県医師会産業医部会を発足させたこと及びその構成、役割、産業医研修会や実地研修の実施状況等について概説した。
シンポジウムに続き、「最近の活動報告」として、森永幸二佐賀県医師会副会長が佐賀県における産業医部会の取り組みを紹介。まず、県内事業場を規模別に見ると、従業者数50人未満の事業者が約97%を占めており、中小企業を中心に産業保健活動を考える必要があるとした。また、2019年の働き方改革関連法施行を受け、佐賀県医師会産業医部会を発足させたこと及びその構成、役割、産業医研修会や実地研修の実施状況等について概説した。
その上で、2014年に厚労省が産保センター、メンタルヘルス支援センター、地産保を一本化することとし、同年に「佐賀県産業保健総合支援センター」が設置されたことを紹介。その所長及び運営主幹が県医師会に委嘱され、多岐にわたる活動を実施していることを報告した。
更に、従業者数50人未満の事業場に面接指導や保健指導等のサービスを提供することを目的とし、県内に四つの地産保を設置したことを紹介。小規模事業場の従業者のメンタルヘルスケアに対し、地産保が果たす役割は非常に大きいとする一方、登録産業医が足りない状況があり、ストレスチェックの義務化や高ストレス者の相談・指導ができない可能性があることに言及し、解決に向けた対応を進める必要があるとの認識を示した。
その他、(1)県内の産業医の約3割が「経験が無い」「専門科以外のことに対応できない」といった理由で産業医活動をしていない、(2)産業医側と事業所側でニーズにギャップがある―等の理由により、事業場と産業医のマッチングが成立しにくい現状があることに言及し、これらの課題解消のため、産業医部会において懇談会やマッチング支援を実施していることを紹介した。
協議
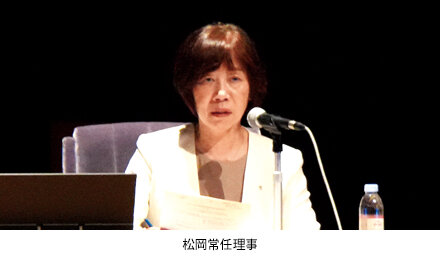 その後の協議では、松岡常任理事が事前に寄せられていた質問に回答した。
その後の協議では、松岡常任理事が事前に寄せられていた質問に回答した。
秋田県医師会からの、「既存の産業医の高齢化が進む一方、新規産業医の育成が進んでいない現状がある上に、地方では基礎研修会を受講すること自体も困難になっている」として、日本医師会の対応を問うたことに対しては、基礎研修のブロック単位開催・サテライト開催の他、生涯研修で使用している日本医師会Web研修システムを基礎研修でも活用することを今後の産業保健委員会で検討していく意向を明らかにした。
北海道医師会からの、「日本医師会認定産業医の手続きにMAMISと連動した審査登録料収納システムを導入する見通し」に関する質問には、日本医師会としてその必要性を認識しており、クレジットカードによる決済機能を搭載した日本医師会Web研修システムの活用も含め、検討を進めるとした。
 その後は、茂松茂人副会長が総括を行い、協議会は終了となった。
その後は、茂松茂人副会長が総括を行い、協議会は終了となった。
当日の参加者は会場での参加が52名、WEB会議での参加が383名、合計435名であった。



